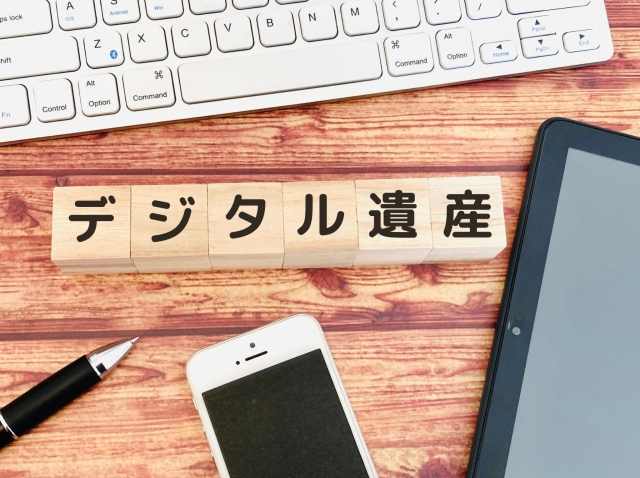スマートフォンやクラウドサービスを日常的に使う人が増える中、財産の一部として「デジタル遺産」の存在が注目されています。
SNSやネット銀行、写真・動画などは、見えにくくても大切な資産のひとつです。
そこで今回は、終活の一環として取り組むべきデジタル遺産の整理と継承方法についてご紹介します。
デジタル遺産を見える化し、終活の第一歩を踏み出す
まずは、自分の持つデジタル資産がどのようなものかを整理することが大切です。
具体的には、スマートフォンやパソコン内のデータだけでなく、SNSのアカウント、クラウドストレージ、オンライン銀行口座、仮想通貨、サブスクリプション契約、メール、写真や動画といった個人データまで幅広く含まれます。
これらを一覧にまとめ、IDやパスワードを安全に管理しておくことが基本です。パスワード管理アプリや、信頼できるノートを活用し、家族にわかる形で保管しておくとよいでしょう。
加えて、エンディングノートや遺言書に情報を記録し、信頼できる家族や知人に共有しておくことで、相続時の混乱を防げます。不要なアカウントや契約については、生前に解約しておくと、残された人の負担も減らせます。
相続時のトラブル回避には、正しい対応と専門家の活用を
本人が亡くなったあと、デジタル資産は相続財産として扱われる可能性があります。
そのため、遺族が独断でスマートフォンやSNSを処分・削除してしまうと、後々のトラブルにつながるおそれがあります。
特に、仮想通貨やオンライン口座などの金融資産がある場合には、法的に正しい手続きが求められます。ロック解除が困難な端末や、データ復元が必要なクラウドストレージなどには、専門業者の力を借りると安心です。
信頼できる業者に依頼することで、大切な思い出や資産を安全に取り出すことが可能になります。
アプリや終活支援サービスを使えば、整理も簡単に進められる
デジタル資産の整理は、専用アプリを使うことで身近に感じられます。「つなぐノート」などの終活支援アプリは、家族と情報を共有したり、エンディングノートを簡単に作成したりするのに便利です。
また、「わたしの未来 終活準備ノート」では、相続や葬儀に関するコラムを読みながら、終活に必要な基本的な知識を学ぶことができます。
さらに、2025年2月より株式会社151-Aとエコパソ株式会社が提携した「デジタル終活ワンストップサービス」が開始され、相談から記録の保存まで一括でサポートを受けられるようになりました。
これらのサービスを活用すれば、誰でも無理なくデジタル終活を進めることができます。
ただし、2025年7月時点では、法的に効力のある遺言書は紙ベースの「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」のみとされています。デジタルでの遺言作成は法整備が進行中のため、現段階では紙による記録を優先することが安心です。
まとめ
見えにくいデジタル遺産こそ、早めに整理しておくことが終活の大切なポイントです。
自分の情報を正確に把握し、必要なものを家族と共有しておけば、万一のときもスムーズに対応できます。
アプリや専門サービスを上手に使いながら、無理なくデジタル終活を始めてみてはいかがでしょうか。